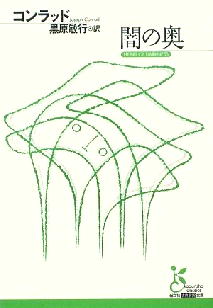
ぼくの中ではどうもコンラッドとメルヴィルが海と難解さという点で大いに重複する作家なのだ。つい先日メルヴィルの小品「ビリー・バッド」を読了し、間をおかずに本書を読んだわけなのだが、難解さという点では本書のほうが格段に上だった。
「闇の奥」は船乗りマーロウの一人語りで進められてゆく話だ。若い頃に彼が経験した出来事を現在の船乗り仲間に語って聞かせるのだが、これが異常な熱意をもって語られる。アフリカの奥地、コンゴ河を遡行する一人の男を捜すこの冒険行は、とりたてて凄い出来事もなく劇的な展開もないし、むしろある程度の退屈さを余儀なくされるくらいなのだが、読んでいるとついつい引き込まれてしまう。本書を読了したとき、心に残るのは悲惨な末路だ。しかし、それはマーロウの一人語りによって強烈に印象づけられたものであり、実のところそれが真実なのかどうかはわからない。本書のおもしろいところはそこなのだ。
マーロウという男が語る話は彼の主観ですすめられる。おそらくそこにはマーロウの心象や思惑そしてもしかすると思い違いなども含まれているのかもしれない。信用できない語り手とまではいかないが、彼の話は細部にまでわたって巧みに描写されるがゆえの熱気とリズムを孕み一つの到達点にむかって集約されてゆく。しかしそれはマーロウという男の目を通して描かれるがゆえに彼の信じるものと主張が幅をきかせた独りよがりなものとなってゆく。コンゴの奥地で象牙を集めるクルツという密林の王のことをマーロウの目を通して描写された読者にとって強烈に印象に残るのはやはりクルツの肖像だろう。物語の最後までその正体をあらわさないこの地獄の王の姿は彼の最期の言葉の印象と共に強烈に心に食い込んでくる。
果たしてその印象をそのまま信じていいものか?河を遡行する奥地への旅は地獄行なのか?抽象と心象の合間で多くの解釈を呑み込んだ闇の奥は底知れない。