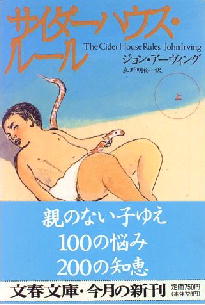
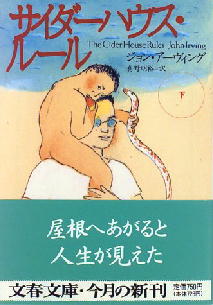
本書の舞台はメイン州の片田舎セントクラウズにある孤児院。まだ第一次大戦が終結して間もない頃、一人のみなし子が生まれるところから物語は始まる。その子の名は、ホーマー・ウェルズ。彼は孤児院でみなの愛情のもと立派な青年に成長する。そして彼は院長のラーチによって「人の役に立つ人間になれ」と教えられる。またこの孤児院では中絶手術も行っていた。この時代、堕胎は法律で禁止されていたのだが、孤児院の院長ウィルバー・ラーチは、望まぬ子を身ごもってしまった女性たちのためにその違法行為を自らの信念のもと神の業として施していた。孤児として育ったホーマーはしかし、その行為に反感をもつ。まだ人の形をしていないとはいえ、それは生を受けた人間の子どもなのだ。その生命を絶つという行為は神をも畏れぬ行為なのではないか。やがて、ひと組のカップルがまた望まれぬ子を中絶しようと孤児院にやってくる。そして、それがホーマーの人生を変える出会いとなったのだが・・・・。
いつものごとく、本書でも大きなテーマとして家族の愛が描かれる。それはアーヴィングが信じるディケンズに代表される十九世紀の小説作法(事実、本書の中でもディケンズの「ディヴィッド・コパーフィールド」とシャーロット・ブロンテの「ジェイン・エア」が何度も登場する)にのっとって濃密に饒舌に語られてゆく。ぼくは本書を読んで久しぶりに読了するのが寂しいと感じた。愛すべき登場人物たち。起伏に富んだストーリー。時間と空間を超越する自在な筆運び(ここが十九世紀の小説とアーヴィングを隔てるところ)と、いつものことながら彼の小説はとても魅力的だ。いままで読んできた彼の作品(「ガープの世界」「ホテル・ニューハンプシャー」「オウエンのために祈りを」)でことさら強調されていた突然絶たれる日常の営みのような人生が直面させる残酷な仕打ちも鳴りをひそめ―――――でも、要所要所には軽いジャブが放たれるのだが―――――平静な気持ちでこの世界と向き合えたのも新鮮だった。
人が生きてゆく上でルールは必要だ。大義として、もちろんそこでは道徳と倫理が優先されており、社会においてアウトサイダーの側には立たないよう配慮されている。そういったルールもあれば、自分の信念で貫きとおすルールもある。ホーマーにとってそれはラーチから教えられた「人の役に立つ人間になる」ということだっだ。望まれぬ子として生を受けた子は、望まれる人になることに自分の存在意義を求めたのだ。彼はそのルールにしがみつき、それに縛られ生きてゆく。そして、最終的にはそのルールを尊重して反感を呑み込み落ち着くべき場所に落ち着く。大団円。
上記のとおりアーヴィングの本をすべて読んでいるわけではないが、本書は数ある彼の作品の中でもかなり上位にくる出来なのではないかと思う。いままでぼくの中ではアーヴィングといえば「ガープの世界」だったのだが、どうやら今後は真っ先に本書の名が出てきそうである。