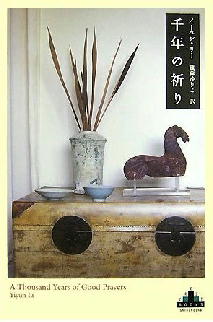
クレストブックスの最新刊は、中国出身の新鋭イーユン・リーの短編集だ。向こうでは『もっとも有望な若手アメリカ作家』に選出されたりして、すごく話題になっているらしい。こういう異文化圏から進出して母国語ではなく英語で作品を書く作家には特に注目してしまう。ジュンパ・ラヒリとかカズオ・イシグロとかヤン・マーテルとか、みんな注目に値する作家ばかりだから自然そうなってしまうのだ。
本書には10篇の短編が収録されている。一読して感じるのは中国という頑固な国の異質な文化である。閉鎖的で、抑圧の多い束縛された世界。古い慣習にとらわれ、新しいことを忌み嫌う世代間の確執。
ぼくなど、これなら動物園の檻の中のほうがマシじゃないかと何度も思った。
当たり前だが、そんな世界でも人と人は干渉しあってお互いを思いやり寄り添って営みを続けていく。
自分の生きる世界を受け入れて、それに流されて生きる者と束縛を怖れ自由に羽ばたこうとする者。
それは自然、世代間の確執となって浮上してくる。生まれた国が悪かったと呪っても状況は変わらない。
だから自由の国アメリカがとても光り輝いて見えるのだろう。
印象に残ったのは「市場の約束」のなんとも形容しがたいラスト。ここで描かれるのは、いつまでも結婚しない娘と母親との関係なのだが、男の肩をナイフで切り裂く行為がとても官能的だった。
「息子」では母親と息子の確執が描かれる。これはそのまま日本に置き換えても通用しそうな作品。
「あまりもの」や「縁組」で描かれる世代を超えた恋愛も新鮮だった。これは日本ではちょっと考えられない。
「死を正しく語るには」は、どことなくユーモアの漂う作品。文化大革命は、様々な影をこの広大な国家におとしている。
「柿たち」は予想もつかない展開に翻弄されてしまった。まさか大量殺人が出てくるとは思わなかった。状況が徐々にあかされていく構成が秀逸。
表題作でもある「千年の祈り」は父と娘の確執が描かれている。アメリカに渡った娘を訪ねていく父。父の存在を疎ましく思う娘。後で気づいても遅いという真実が痛いほど染み込んでくる作品だった。
ざっと印象に残った作品について言及したが、実際のところぼくはまだこの作家の本質がつかめていないと思っている。印象深い短編集だったが、心にまでは響かなかった。例えばラヒリの短編集の時は、こんな作家に出会えてほんとうに良かったと神に感謝したくらいなのだが、この短編集ではその感動が得られなかった。良い作品だとは思うのだが、いまいち心に浸透するものがなかった。これからの作品で見極めよう。