
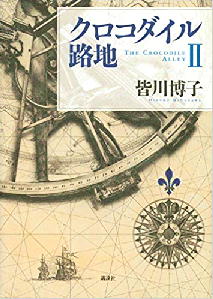
すべては冒頭の一行『竪琴の全音階を奏でるような、秋であった。』に集約される。長大で、まるで異世界のような馴染みのない場所と時間を切り取りながら、そこに展開する物語は精緻を極め、かろやかに自由に羽ばたく。
しかし、ぼくはそこに旨味を感じない。皆川博子の本領が発揮された作品だとは思えないのである。かといって、本作が駄作だというのではない。先にも書いたとおり世界は精緻をきわめ、壮大な復讐の物語として十全に機能しているし、最後まで読み通させるストーリーテリングは健在だ。
でも、これをもって皆川博子の最良の部分を感じるとは言い難いのである。
でも、これをもって皆川博子の最良の部分を感じるとは言い難いのである。
フランス革命の狂乱とその抗えない運命に翻弄される人たち。上巻ではフランス、下巻ではその登場人物たちがイギリスに移ったあとの物語が描かれる。イギリス編では、あの「開かせていただき光栄です」に登場したメンツも顔を出し、世界観の共有に高揚する。
しかし、しかしだ。ぼくはここにきれいに洗われて白く輝く美しい皿のような空虚を感じてしまう。林立する透明なグラスのような寒々しさを感じてしまう。いつもなら、ぼくの大好きな皆川短編なら白く細い女性の脚のようなエモい衝動を感じさせてくれたり、ピンッと張りつめたピアノの鍵盤の一打のように頭に突きささる言葉の衝撃を感じさせてくれたり、目の前で傷口を広げるみたいな嫌悪を感じさせてくれたりするのに、本書にはそういうインパクトが皆無だった。
みんなが春を待っている。秋に始まった物語は夏がきても冬がきても春を待っている。運命は、翻弄する。無条件にみんなを運び去る。時と共犯する運命に抗うことはできない。誰も。狼煙をあげろ!運命に抗う狼煙をあげろ!しかし、しかしみんな運び去られ、連れ戻される。運命に従順であれ。抗うことはできない。人は、流されるだけ。
竪琴の全音階を奏でるような楽音を、ぼくは聴いた。